『近畿地方のある場所について』っていうホラー小説、正直ナメてたんだけど…読んだらマジでゾクッときたやつ!
「呪いが始まる」とか「読んだ人が巻き込まれる」とか言われてるけど、読んでるうちに「え?これほんとにフィクションなん…?」って錯覚しちゃうくらいのリアリティ。
三種類の怪異とか、構造的な怖さとか、ただの「怖い話」じゃ済まない深みがあって、語りたくなることだらけ!
- ✔ 小説『近畿地方のある場所について』の全体像と構造的な怖さ
- ✔ 三種類の怪異の正体とその繋がりに関する深掘り考察
- ✔ 書籍版とカクヨム版の違いや映画化の見どころポイント
『近畿地方のある場所について』の構造と本質を解き明かす
背筋さんの『近畿地方のある場所について』って、単なるホラー小説って思ってたけど、読めば読むほど深くてヤバい…。
怖いだけじゃなくて、読み進めるうちに「え、これ何の話だったの?」ってなるくらい構造が入り組んでるのよ。
モキュメンタリーっていう形式だから、ドキュメンタリーとフィクションの境目があいまいで、マジで「これは作り話なの?実話なの?」ってなる不思議な感覚。
物語の鍵を握る三つの怪異とは?
この作品、全体を通して「三種類の怪異」が絡み合ってるんだよね。
まずは山の奥に住む白い大きなモノ(=「山へ誘うモノ」)っていう存在。
それから赤い服を着たジャンプ女と呼ばれる女性、そして最後に、命を喰らうって噂されるあきらくん。
どの怪異もバラバラに見えて、ちゃんと繋がってるのがこの物語のゾッとするところ。
個人的には、それぞれの怪異が世代や時代にリンクしてる感じがして、読み応えバツグンだった。
舞台はどこ?生駒山との関係性とモデル地の考察
作品中では「●●●●●」って伏せられてるんだけど、多くの読者がモデルは生駒山じゃないかって言ってるんだよね。
大阪府と奈良県の境目にある山ってことで、心霊スポットが多いのも共通点。
ただ、作中では生駒トンネルも個別に出てくるから、あくまで生駒山はイメージのベースであって、実在の場所ではないっぽい。
この「どこかにありそうでない場所」っていう設定が、より一層のリアリティを増してて、背筋さんやっぱすごい。
「読むことで呪いが始まる」構造的恐怖の仕掛け
この作品のやばいとこはね、「読んでる人も巻き込まれる」構造になってるとこ!
作中で「呪いのシール」とか「ネットのコメント」が出てくるんだけど、それが読者自身の記憶に訴えかけてくる作りなんだよ。
とくに最後に出てくる「見つけてくださってありがとうございます」ってセリフ。
これ、マジでゾワッときた…。
「あ、今私、呪いに関わっちゃった?」って思わされるから、夜中に読むと後悔するやつ(笑)。

怪異①「山へ誘うモノ」とは何か?
まず最初に出てくるのが、この白くてでっかい謎の存在。
通称「まっしろさん」とか「まさる」とか呼ばれてるけど、何者かはっきりとはわかってないのがまた怖いんだよね…。
でもこの存在がすべての元凶っぽくて、もうほんと、読んでて鳥肌レベル。
白い男「まっしろさん」=まさる説を検証
このまっしろさん、元は「まさる」って名前の男だったって言われてるの。
昔の村で女の人に柿の話ばっかりして嫌われて、最後は岩に頭ぶつけて死んだっていう、ちょっと悲しい話があるんだよね。
その後、村人が「これは祟りになる!」ってことで祠を作って祀ったらしい。
でも、時間が経って忘れられた結果、再び動き出して“嫁”を求め始めたっていう。
つまり、山の怪異ってだけじゃなくて、忘却された怨念の集合体かもしれないって考察、マジで興味深い。
祠と御神体の移動、呪文に仕込まれた意図
で、この山の神様的存在を祀ってた祠の石(御神体)なんだけど、今はカルト教団の施設に移動してるの。
「スピリチュアルスペース」っていう謎の団体ね。
呪文にも「ましら」って言葉が紛れ込んでて、もう完全にリンクしてるでしょってなる。
これは、まさる=ましろ=ましらっていう同一視の演出だと思う。
呪文を唱えることで、自分が山の怪異の代理人になったり、誰かを誘導したりできるっていう設定、普通にこわすぎる。
人を使った誘導、ネットとSNSによる拡散の構造
この怪異のもう一つヤバいところは、人間を使って女性を山に誘い込むってとこ。
学校の遊び「まっしろさん」でも、男子が女子を追いかける設定で、協力者が出てくるのがもう異様。
しかも、それが現代ではSNSやネット掲示板での投稿に形を変えてるのが、ほんとに怖い。
「山に行きませんか?」って誘う不審者が、ただの変質者じゃなくて呪いの代理人っていう発想、天才か。
都市伝説がリアルに近づく瞬間って感じで、これ読むとちょっとでも山の話聞いたら即逃げたくなる(笑)。

怪異②「ジャンプ女」の正体と呪いの継承
次に出てくるのが「ジャンプ女」って呼ばれる存在なんだけど、これがまた切ないような怖いようなキャラでさ。
赤いコートを着た女性で、死んだ息子を蘇らせようとしちゃったせいで、色々おかしくなっていくんだよね。
でもその背景にはカルト教団とか子どもの死とか、ちょっと重たいテーマがあって、読みごたえがエグいのよ…。
息子の死から始まる母の変貌と呪いの拡散
このジャンプ女、もともとは普通の母親だったの。
でもね、息子の了あきらくんが首を吊って亡くなったのがキッカケで、精神的に壊れてしまった。
あきらくんの死は、「まっしろさん」の遊びが過激化して、身代わりとして殺された説が有力って言われてるよね。
で、その死体を見つけてジャンプしてた母親の姿が、あまりにも印象的だったから「ジャンプ女」って呼ばれるようになったの。
つまり彼女は怪異になった人間なんだよね。
「赤い女」の怪異化とメディアを使った戦略
ジャンプ女の怖いとこって、普通に電波とかネットを使ってくるところ!
彼女、自分の息子を蘇らせるために呪文を使って、結果的に悪魔を生み出しちゃったんだよね。
でも、それを「育てるため」に他人に呪いを広めるっていう暴走モードに突入。
ネットでの怪談話、SNSでのシェア、コメント欄での勧誘…今の時代っぽい方法で怪異の拡散をしていく姿、マジで背筋ゾクゾク。
「読むことで呪いが始まる」っていう仕組みは、まさにジャンプ女の意図的な演出なのかも?
貼られた鳥居の絵と呪文の意味を考察する
ジャンプ女が特にこだわってたのが、あの「鳥居の絵」と「呪文」だよね。
四隅に「女」とか「了」って書かれた鳥居の絵、あれ貼った場所に怪異が発生するっていう…マジで無理案件。
呪文の中に「ましら」って言葉が出てくるけど、意味は不明ってされてて、逆に怖い。
しかも、電子機器越しに怪異が広がるって演出が、もう現代人の生活丸ごと侵食してくる感じで、ゾッとするしかない…!
ジャンプ女の呪いは、ただの祟りじゃなくて、意図的な情報戦ってとこが本気で怖いんだよ。

怪異③「了あきら」=命を喰らう悪魔の本質
ラストに登場するのが、「了あきら」って名前の少年。
この子、死んだあとジャンプ女によって呪いで蘇らされたんだけど、もはやそれは本人じゃなくて悪魔。
彼が登場してから話がグンとホラーからダークファンタジーに寄ってくるのが印象的。
母によって蘇生された「悪魔」の目的とは
最初はただの哀しい母と子の話かと思いきや、ジャンプ女が呪文を使って蘇らせたあきらくんが、完全にヤバいやつだったってオチ。
彼は命を喰う存在として描かれてて、もう人間でもなんでもない感じ。
見た目は子どものままなのに、やってることはマジで悪魔そのもの。
ペットを連続で飼い続ける人のエピソード、あれ、ほんと鳥肌だったよね。
命を捧げ続けないと生きていけない存在って、やっぱり何か根源的な恐怖を感じる。
餌としてのペット、悪意の連鎖の先にあるもの
悪魔あきらに憑かれた大学生が、メダカ・ハムスター・インコ・猫・犬…と次々飼ってるって話、もう地獄。
それ全部身代わりにしてるっていうの、ちょっと悲しすぎない?
しかも、命を捧げてもいずれは足りなくなる、っていう終わりのない飢えも描かれてて、読んでて胃が痛くなる…。
人間って、いざとなったら誰かの命を「交換可能」って思っちゃうんだなっていう、すごい皮肉なテーマでもある気がする。
都市伝説と子どもたちに語り継がれる恐怖
最終的にこのあきらくんの存在は、学校の怪談や都市伝説にまで広がってるのが怖すぎる。
「ましろさん」「あきおくんの電話ボックス」とか、もう完全に伝説化してて、リアルに学校で語られてそう。
ネットで広まるだけじゃなくて、子どもたちの口伝えで広がっていくの、ほんと止めようがない感じする。
それがジャンプ女とあきらの狙いだったとしたら、めちゃくちゃよくできてる話。
読み終わったあとも、なんとなく日常の中にこの存在が潜んでる感じがして、忘れられない…。

書籍版とカクヨム版の違いを徹底比較
この作品、もともとは小説投稿サイト「カクヨム」に掲載されてたんだけど、後に書籍化されてて、実は中身ちょっと違うの!
「無料で読めるからそっちでいいじゃん」って思ってたんだけど、比較してみたら「え、こっちのエピソードは書籍だけなの!?」ってなってビックリ。
ってことで、今回はカクヨム版と書籍版の違いについてまとめてみたよ!
追加エピソードが示す山の怪異の深層
まず大きな違いは話数。
カクヨムは全34話、一方で書籍版は全40話になってるの。
単純に6話増えたっていうより、構成を再編成したり、話の厚みが増してる感じ。
特に書籍に追加された「カラオケ」や「見えたもの」のエピソードは、山の怪異が本当にただの人間やモノじゃないってのを裏付けてて、読み応えマシマシ。
私的には、「この話、映画化の伏線じゃん!」って思っちゃった(笑)。
構成変更で見えてくる怪異のつながりと歴史
カクヨム版では、「まさる=人間の怨念」って話で終わってたのに、書籍版ではもっと古い祠の存在や、神社の由緒にまで話が広がってて、背景がめちゃくちゃ深くなってるの!
「あ、まさるが始まりじゃなくて、もっと前から続く呪いなのかも…」って気づくと、背筋ゾクゾク。
しかも書籍版では、「最後のまとめ話」が超ロングバージョンになってて、整理されたようで逆に混乱させてくるという…。
でも、それがこの作品の醍醐味よね。スッキリしない恐怖ってクセになる。

「近畿地方のある場所について」原作から映画化への展開
なんとこの作品、ついに実写映画化が決定!
2025年8月8日に公開ってことで、もうVOD大好き人間としてはこれは劇場で観るしかないでしょ。
あのモキュメンタリー形式をどうやって映像で表現するのか、マジで楽しみなんだけど…怖すぎて途中で目そらしそう(笑)。
実写映画の公開情報とストーリーの再構築
映画版は、ジャンプ女とあきらくんのエピソードを中心に展開されるって噂もあるみたい。
「読むことで呪いが始まる」っていう構造が、映像でどう拡張されるのかめちゃくちゃ気になる!
もしかして、劇中に鳥居の絵とか出てきたら、それ撮ったらやばい系…?
背筋作品ならそれくらいやりそうで、逆にワクワクしてる。
原作のどこまでが映像化されるのか?
原作ってかなり話数あるし、時系列もバラバラだから、映画でどこまで拾うかは気になるところ!
「あきらくんとジャンプ女」まではたぶん確定で、それ以外はエピソード的にちょこちょこ入れてくるパターンかも?
でも、ネット上の拡散描写とか、都市伝説の演出とかは映像の方が効果的だと思うから、そこ期待してる!
そして映画観た人が「見つけてくださってありがとうございます」って言われたら…ゾワッとするでしょ(笑)。

- ★ 『近畿地方のある場所について』は三つの怪異が交差する物語
- ★ 「読むことで呪いが始まる」構造が作品全体に仕掛けられている
- ★ 書籍版はカクヨム版に比べて追加エピソードが豊富
- ★ 実写映画化によって新たな恐怖の伝播が始まろうとしている
- ★ 情報・記憶・呪いの連鎖を現代社会と照らして考察できる作品

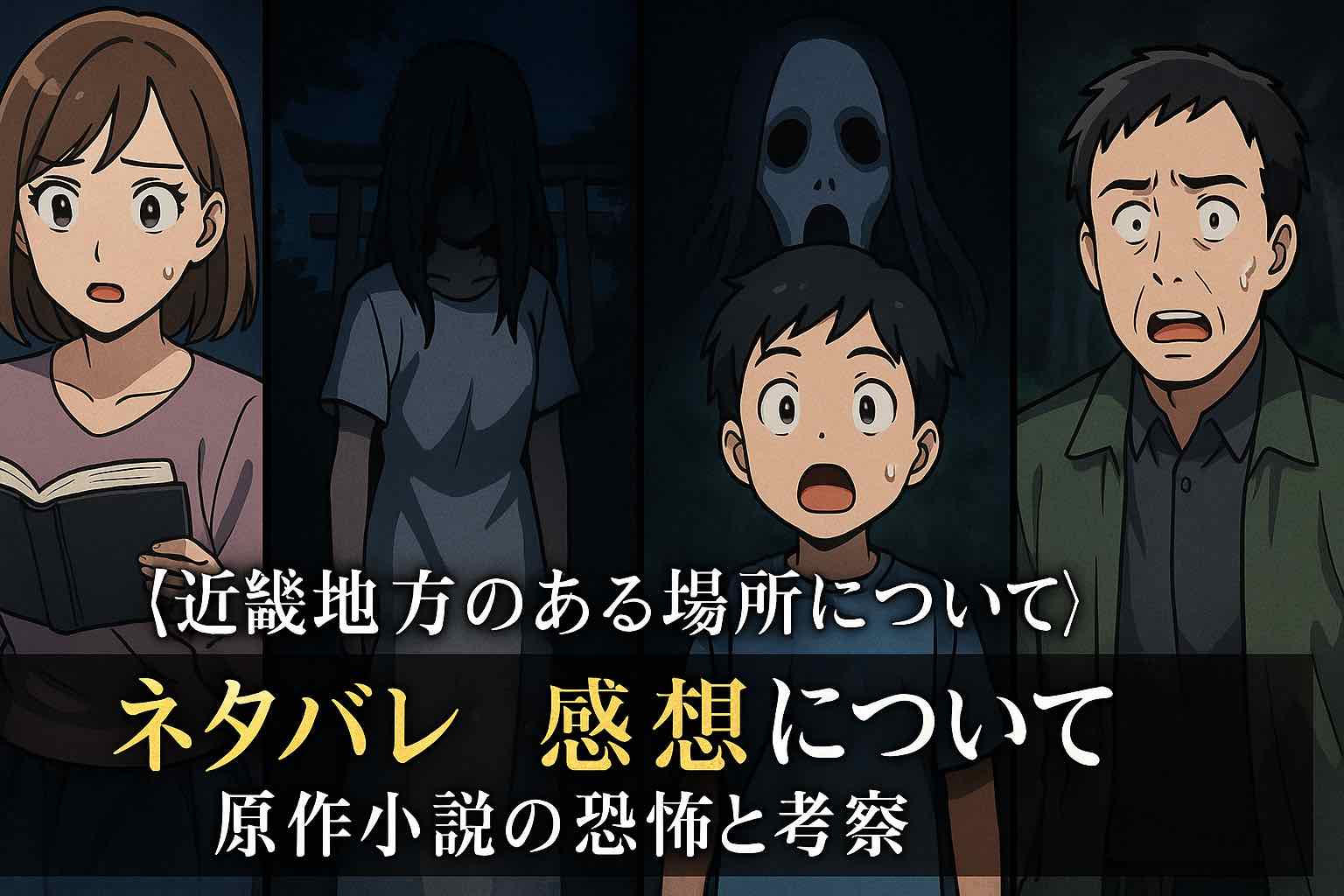


コメント